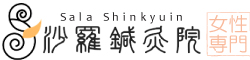鍼灸の歴史
鍼灸は、中国を起源として2000年以上前に治療法が確立された東洋医学で、
日本へは仏教の伝来と共に1400年ほど前に伝えられました。
その後、日本人の体質や文化に合わせて「漢方医学」として独自の発展を遂げます。
以来、西洋医学にその座を明け渡すまで、
健康維持のために人々の病気による悩みを解決する手段として、
長い歴史の中で脈々と受け継がれてきました。
現代では、代替医療として西洋医学では説明のつかない難病の治療や、
西洋医学的な治療法ではなかなか治らない病気の治療、
または、西洋医学では病気としてみなされないさまざまな症状を和らげる治療法として、
多くの人々に利用されています。
鍼灸は東洋医学
鍼灸の理論は、中国の伝統医学である中医学が基になっています。
「四診」と言われる東洋医学的な診断法から体質や症状をしっかりとチェックした後、
気血津液理論・陰陽五行論・三陰三陽論や傷寒論などなど、
いくつかの理論を組み合わせて証(東洋医学的な診断)を立て、
それぞれの身体に合わせて鍼や灸を行います。
同じ病気でも「四診」によって、
「病巣が浅いか深いか」
「体質的なものが原因か、外部からの病邪が原因か」
「体内に熱がこもって起こったのか、体が冷えて起こったのか」
といった病気の性質によって、鍼をする場所や打ち方、刺激量も変わってきます。
鍼灸がオーダーメイド医療と言われる所以です。
西洋医学と東洋医学

| 西洋医学 | 東洋医学 |
| からだを細分化して考え、 患部を中心に診る。 健康診断や検査で早期発見を心がけ、病巣が見つかっった場合は 徹底的に叩く。 専門的な分野で深く病気を探ったり、一刻を争うような大怪我や血管などの手術が得意。 |
からだをホリスティックに捉え、 一部の症状だけを見るのではなく、 こころとからだ、全体を診て そのアンバランスを調整することにより、 その人本来の自然治癒力・免疫力を 回復させ、病を治すことを目指す。 現代西洋医学では説明のつかない難病の
治療や慢性病にも効果を発揮する。
|
鍼灸治療は東洋医学がベースになった1つの治療法です。
からだの自然治癒力を増大させ、免疫力を高め、新陳代謝を促します。
からだの「治る力」を呼び覚ますので、単に病気を治すだけではなく体質から改善することができます。
全体のバランスを診るため、原因や病名がはっきりしない症状にも効果を発揮します。
副作用は全くない訳ではありませんが、西洋医学による副作用に比べればとても軽いものです。
未病を治す
東洋医学には「未病に治す」という考え方があります。
病が重くなる前に、そのサインに気づき治療することで、重篤な病気にならないようにする、
という考え方です。
このことから、東洋医学は「予防医学」と言われることもあります。
「未病を治す」ためには、日ごろの生活習慣に気をつけたり、
自分に合ったセルフケアをすることでも病を防ぐことができます。
でも、すべてを自分1人でコントロールすることが難しいときもあります。
ましてや、体調の悪いときは誰でも精神的にも不安定になりやすいもの。
そんなときは1人で抱え込まず、ぜひ鍼灸の力を借りて本来の自分を取り戻してください。
未病・健康・病気の違い

| 未病 | 身体の恒常性(ホメオスタシス)が崩れかかって、病気が発生する前の状態。 eg.肩こり・冷え症・身体が重い・食欲がない・やる気が起きない・眠りが浅い・朝起き辛い etc… |
| 健康 | 身体的・精神的・社会的に完全に良好な状態であり、たんに病気あるいは虚弱でないことではない。(WHO世界保健機構の定義) |
| 病気 | 身体の恒常性(ホメオスタシス)が崩れ、そのままでは元に戻らない状態。 |