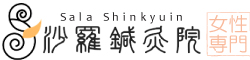※【アトピーがよくなる10の基本事項】と題して、アトピーをよくするためには、これだけは基本中の基本!というものをまとめました。
※アトピー・プログラムなどでお渡ししている「アトピーを劇的によくするための10のセルフケア」PDFファイルの内容と重複している部分もありますが、セルフケア以前の、基本中の基本について書いています。
アトピーのセルフケアの中でも、お風呂問題は意見の分かれる問題の1つです。
こればかりは保湿や、どの塗り薬を使うのかと同様に、その人のライフスタイルや、そのときのお肌の状態によって答えは違うし、季節によっても異なります。
それに私たち日本人にとってお風呂は、ただ単に身体を清潔にするためだけのものでもなかったりするからです。
ですが、私はあえて「お風呂に入る」ことを提唱したいと思います。
(お風呂に入らない派の方、ごめんなさい。)
もちろん、毎日お風呂に入る必要はありません。
お風呂に入ることを勧める最大の理由は、皮膚についた雑菌やウィルス、汗や皮脂による汚れを落とし「清潔を保つため」だからです。

アトピー肌の人が入浴するときに注意するべきこと3つ
アトピーをよくするために「清潔を保つ」目的で、アトピー肌や乾燥肌の人が入浴するときには、注意点が3つあります。
 お風呂の設定温度は42℃以下
お風呂の設定温度は42℃以下
熱いお湯が気持ち良いのは入ったその瞬間だけ。
熱いお湯は皮脂を奪い、お肌の乾燥を促進します。
寒い冬でも42℃くらい、暑い夏なら39℃以下ぐらいの設定温度にしましょう。
 長湯は避ける
長湯は避ける
お風呂に入っている時間が長ければ長いほど「皮脂が奪われる」と思っておいた方が賢明です。
アトピー性皮膚炎の湿疹など皮膚の炎症がある状態の肌は、健康な肌の状態より、お肌のターンサイクルが早くなっています。
一般的に長湯をする目的の1つは、湯の温熱により肌の新陳代謝を促してお肌のターンサイクルを促し、美肌を作るためと思うのですが、皮膚の炎症や乾燥がある場合に限ってはマイナスに作用することがあるのです。
シャワーでも十分ですが、お風呂のリラックス効果も捨てがたいので、5分以内ならお湯につかっても構いません。
アトピーの方で長湯が好きな方の目的は、冷えや疲労の回復のために血流を改善したい、リラックスしたい、汗をかきにくいために汗をかいてデトックスしたいなどのはず。
それならば、足湯でも十分に効果を得ることが可能です。
保温が可能な足湯器ならば、30分でも1時間でも長湯を楽しめ、なおかつお肌への負担は最小限に抑えることができます。
 石鹸は使わないか、使用する場合は天然油脂由来のものを使う。
石鹸は使わないか、使用する場合は天然油脂由来のものを使う。
汗水垂らして仕事をするような職種の方でもなければ、皮膚についたさまざまな雑菌やウィルス、汗や皮脂などの汚れは、お湯で80%落ちると言われています。
ですから全身を石鹸でくまなく洗う必要はありません。
アトピーの原因の1つに過剰に清潔にし過ぎるライフスタイルがあります。
石鹸を使うのは陰部や皮脂の分泌の多い部位のみで十分です。
ただし、体育の授業や課外活動で大量に汗をかいている子どもたちや、運動や労働でたっぷりと汗をかいた後は、適宜、石鹸を使って体を洗いましょう。
石鹸は高価なものを買う必要はありませんが、天然油脂由来のものを選ぶようにしましょう。
石鹸を手作りするのもおススメです。
ボディソープなど液状のものは界面活性剤が含まれているため、使用は避けた方がいいでしょう。

世界基準は「入浴は毎日しない」
アトピーを抱えている人にとって、入浴問題は重要なテーマの1つ。
脱入浴を提唱される方の理論も分かります。
私は何年か続けてネパールへボランティアへ行っていた時期がありました。
湯船につかる、という習慣のない、シャワーすら毎日浴びない、もしかすると毎日服を着替えるということすらしない文化の国でしたが、アトピー患者は1人も見かけませんでした。
キレイなお肌を保つためには皮膚の常在菌と仲良く共存することが必要ですが、ネパールの人たちは自然に菌たちと共存生活しているため、強くて丈夫な皮膚を作っているのだと推察しています。
世界を見渡しても、毎日入浴する習慣があるのは日本くらい。
水資源の問題や、環境や文化もあり、「入浴は毎日しない」のが世界基準です。
入浴する目的が、アトピーを悪化させないために「清潔を保つ」ためなら、入浴は2・3日で1回くらいで十分ではないでしょうか。
鍼灸治療は、心と体の調和を目指します。
定期的に受けることで、心身の健康を保つために役立ちます。
心と身体が丈夫になり、柔軟性が向上し、免疫力が高まってきます。
自信が持てるようになり、リラックス、ストレス軽減効果があります。
冷え性・むくみ・慢性疲労・便秘・肩こり・頭痛などでお悩みの方は
根本から体質を改善して健康な身体を作る沙羅鍼灸院へご相談ください。

コチラ↑↑↑をポチっと押して、お友達に追加してくださいね。
お得なクーポンや、季節の養生法などセルフケア情報を配信しています。